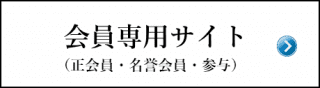参考資料
天然ガスの歴史
陽火・陰火
火は五行の一つであり、気あって質がなく、造化の両間、万物を生殺する。五行はみな一つであるが、ただ火だけは陽火、陰火の二つがある。
陽火は草に遭うとこれを焼き、木があると燔き、湿によって弱まり、水によって消滅する。陰火は草木を焚かず金石を流す。湿によっていよいよ焔え、水に遭うとますます熾んになり、水を差すと光焔は自然に消滅する
陰火の一種に寒火がある。火山軍(山西省河曲・偏関二県の地)地方では土を耕す時、鋤を深く入れると激しい焔が出てくる。これは寒火である。
(出典 李時珍(明)撰「本草綱目」1596)
君火・相火
陽火・陰火のことである。君火は明るさを特色とし、相火は温熱を保持することを本分とする。全ての火を観察するとその気と質に上下がある。そもそも明るさとは光であり、火の気である。位とは形であり、火の質である。一寸の燈明が室いっぱいに明るく広がるのは火の気によるものである。また、炉にみちた炭が熱があっても焔がないのは火の質によるのである。
焔も炭もみな火である。しかしながら、焔が明るい時は熱が弱く、焔が立ち上がらずにこもっている時は熱が強い。気が動ならば、質は静と云える。
(出典 張介賓(明)撰「類経図翼」1624)
風くそうず
日本では、地中から滲み出してきたり、湧き出してきたりする原油は古くから「くそうず」とか「くさうず」と呼ばれてきた。これは、「臭い水」に由来していると推測される。これを受けて天然ガスは「風くそうず」と呼ばれてきた。また、書物には「火井(かせい)」あるいは「風火」と書かれてきた。
エクバタナの火
アレキサンダー大王が全バビロニアを支配下におき、かの地を訪れた時のエピソードがある。
紀元前330年ころ、アレキサンダー大王がバビロニアから更にはるか東方にあるかってのメディア王国の中心地エクバタナ(現在のハマダンのことで、イラン西部にある)において、地上の割れ目から噴水のように火が出ているのを見て驚いた。
また、そこから遠くない所には湖のようになっているナフサの流れがあったとも記されているので、いわゆる随伴性天然ガスが噴出し、燃えていたものと見られる。
(出典 プルタークの「英雄伝」)
拝火教の聖火
ゾロアスターが紀元前にイラン高原を中心に広めた拝火教では、天然ガスや石油の燃え盛る火のある場所に神殿を造って礼拝した。このような神殿遺跡の一つがイランのMasjid-i-Suleiman(テヘランの南西、ハマダンの南東)にあり、その近くで1939年に中東最初の油田が発見されている。
製塩用燃料
紀元前940年ころ、中国では中空の竹によって天然ガスを海辺まで導き、海水を煮沸して塩を作るために使用したと伝えられている。
(出典 IGT(Rebecca L. Busby 編)「Natural Gas in Nontechnical Language」)

昔の中国の掘削リグ
蜀の火井
蜀は3世紀の三国時代に四川を中心に栄えた国である。蜀都賦は中国の天然ガスに関する最古の文字記録と云われているが、そこには蜀の都(現在の成都)付近にある火井が一大名物として紹介されている。
(出典 揚雄(西漢)著「蜀都賦」)
最近の情報によれば四川省の天然ガス生産量は年間70億m3と云われ、主に化学肥料や化学品製造用原料として使われ、家庭用燃料としての割合は10%程度である。
(出典 Omiyaほか「International DME Workshop」2000)
入方村の寒火
越後の蒲原郡入方村(如法寺村)で1661年~1673年頃、初めて寒火を利用した。荘右衛門という村長が家を構えて寒火を囲み、臼で寒火を蔽った。火の光は臼の孔から出て、燈油の明かりを必要としない位の明るさであった。隣家にも筧を斜め横に数本通してこの寒火を取ることを許した。竹木や紙布がこの火の光に触れても焼けない。昼は石で蔽って孔を塞いでおく。こうして今日に至るまで途絶えることがない。これは本草綱目で紹介されてる寒火の類と云える。
(出典 寺島良安編 島田勇雄・竹島淳夫・樋口元巳訳注「和漢三才図会」1712)

1645年ごろ、如法寺村で天然ガスが使われていたことを示す絵
如法寺村の火井
越後の国弥彦駅から南に5里行くと三條という所がある。三條からさらに南に1里行くと如法寺村(入方村)がある。この村に自然と地中から火が燃える家が二軒あり、百姓庄右衛門の家の火の方が大きい。三尺四方の囲炉裏の角に古い挽臼を据え、その孔に箒の柄くらいの竹を30cm余りに切って差し込み竹筒の口に種火を触れさせるとたちまち竹口より火が吹き出す。強く吹き消せばすぐ消える。二三百目ほどの蝋燭を燈しているくらい明るい。竹をつないで導けば遠くでも燈せる。この火は1645年以来絶え間なく燃えている(北越雪譜にも記述があるので200年は続いたことになる)。
(出典 橘南谿著「東遊記」1795)

入方村(如法寺)火井の図(「北越奇談」より葛飾北斎画)
見附川の火井
越後の七不思議として紹介されているもので見附川の舟渡し場では、河原の砂に管を差し込むだけで、何ヶ所からも炎を出して燃えて夜道を明るく照らし出すことが出来たという。
これは現在の見附油田の位置にあたると云われる。
(出典 橘崑崙著「北越奇談」1812)
雪中の火
魚沼郡五日市の西の方に低い山があり、その山裾には小さな池があった。天明(1781~1789)の頃、そのほとりで雪遊びをしていた子供たちが遊びにも飽きて、小枝を集めて火をたいたところ、少し離れた場所で火が燃えあがった。子供たちは驚いてみな四方へ逃げ散った。子供たちの中の一人が家へ帰って其の様子を親に詳しく話したところ、この親は関心の強い人で、その場所へ出かけ燃えている様子を観察するとまだ消えずに残っている雪の中に手が入る程の孔があり、その孔の10cmくらい上で火が燃えていた。この様子を見て、これは正しく如法寺村の火と同類であると考え、火口に石を入れて火を消し、家に帰っても他人には何も言わなかった。
やがて雪が消え頃、現場を調べると火口は池の岸辺にあった。火うちによって発燭(つけぎ)に火をつけ、池の中へ投げ入れると池の水面に火が燃えあがった。水の上で火が燃える様子は如法寺のガスよりも不思議だといって大勢の村人が集まって来た。その後、商才に長けたものが池のほとりに湯屋をつくって筧でガスを湯槽の竈に導いて燃やして湯を沸かしたり、また燈火とした。
(出典 鈴木牧之著「北越雪譜」1837)
地獄谷の火
魚沼郡小千谷の在、地獄谷の火井は如法寺のものより大きい。近年、地獄谷に家を建て、地火で湯を沸かし、客に入浴させており、夏~秋の初めまで遊客が多い。このような火井は他の国では聞かず越後に多い。
先年、蒲原郡の或る家が井戸を掘った折り、その夜に医師がきて井戸を掘ったことを聞きつけ、帰宅のおりに提灯を井戸の中へ入れ、その明かりで井戸を見て帰った。ところが、井戸の中から急に炎が出、火勢激しく燃えあがったので近隣の人たちは火事だと思って駆けつけた。井戸の中より火が燃えあがっているのを見て、このような井戸を掘ったからだと村人たちが口々に主を罵ったので、主もこの火をおそれて埋めたとか。これは正しく陰火である。かの如法寺村の陰火も発燭(つけぎ)を近づけると燃え出したように陽火が無いと燃えない。今回の例も医者が提灯を井戸の中へ下げたからで、陽火によって燃え出したものである。
頚城郡の海辺にある能生宿という所は北陸道の官路である。この宿から山の方へ2里ばかり入ると間瀬口という村がある。ここには如法寺村と同じような火井がある。このあたりは用水が乏しいところで旱魃の折には山腹に井戸を水平に掘って水を得ることがある。或る時、井戸を横に掘り、穴の中が暗かったので松明を用いて照らしたところ陽火を得て陰火が燃え上がり、このために人が焼死した。
以上のような事例を見るにつけ、越後には地火を出す火脈を有する地が多くあり、陽火と接する機会が無いために発火しないでいるものが多いと思われる。
(出典 鈴木牧之著「北越雪譜」1837)
越後の天然ガス
今から約90年前の1907年に天然ガスの特性、由来、その事業化等について述べられたもの。
新潟県長岡近在の畑に在るガス井より噴出する天然ガスは炭化水素ガスと云われるもので、熱を発生する力が非常に強く、煤煙を発生せず、無色透明で燃えやすく、また消火しやすい、故にこれを使用しても危険性が少なく、かの石炭ガス、あるいは「アセチレン」ガスのように嫌悪すべき臭気も全くなく、ガスの中で最も優れていることは、自ら実見したところである。既に昨年、日本天然瓦斯株式会社が組織され、今まさにその利用方法を検討しているところであるが、これは決して各地の資本家及び企業家が傍観していて良いものではない。
学者の説によれば、天然ガスは過去において生成し今日も尚絶えず生成しつつあるもので、その由来として次の三つが挙げられる:
1)炭素を含む物質の緩慢な分解によって生成する
2)石油生成と同一根源から石油と同時に生成する
3)炭素を含む物質及び石油が地下の熱、或いは人工熱作用によって分解して生成する
天然ガスの主成分たる沼気(メタン)は、有機物が水の共存下、常温において酸化作用を受けて生成するものである。成分中の酸素及び水素は漸次分離して、一部は化合して水となり、他は炭素と化合して炭化水素となる。この作用は過去において石炭生成と同時に行われ、また、現今池沼湿地等において、水藻木葉等の堆積する所で常に行われている。池沼の底を撹拌した時に沼気が放散されることは、よく知られている。また炭坑等において石炭が湿気を帯び、自然に分解して炭化水素を生じ、それが集積すると、時として炭坑爆発の原因となることは、よく知られているところである。
石油及び土瀝青も、常温において徐々に分解してガスを発生する。酸、塩基、其の他の酸化剤の作用を受ける場合に特に多い。また硫黄化合物の作用を受けて炭化水素と硫化水素とを発生することがある。「エタン」、「プロパン」等は、メタンのように有機物の常温における分解作用によって生成することはなく、従って天然ガス中にこれらを含むものは石油根源に近いものであるを認識すべきである。即ち石油と共に産出されるか、或いは地下にて石油より分離し、幾らか離れたところに移動して単独に存在するものであること知るべきである。二酸化炭素は常温では生成せず、火山作用の如き、地熱の高温度にふれ炭素質物体の分解によって生成したものであろう。天然ガスが火山岩地方変成岩所在地に現存し、また鉱泉に伴って産出されるのはこの生成根源を証明していると云える。
以上のような学者の説く所から考えると、天然ガスはかの石油とは大変趣を異にし、過去において生成しただけではなく、今もなお絶えず生成しつつあるものと云え、従って天然ガス井の寿命は石油井のように短いものではない。唯々、従来の実験によれば天然ガス井の鉄管内には、時間がたつと鉱物質が沈殿し、また砂石を吹き上げて坑井を閉塞させ、水やガスの湧出を阻止することがあり、使用者はこのような障害に困ったと云われる。しかし、これを除去する方法はある。例えば新らたにガス坑井をその付近に掘削して旧坑井に代えることが出来る。
天然ガスの大噴出は、たとえ無限ではないにせよ、決して短い歳月の間に欠尽するものではないので、その付近に工場を建ててその動力を天然ガスに求めることが出来る。また、これを他の都市に輸送して、燈火用や工業用に供給することも有利な事業と云える。これが越後の天然ガスを世に広く紹介して、資本家や企業家の注意を喚起しようとする理由である。
(出典 東京ガスがす資料館年報No.3:原典 東京経済雑誌1907)
茂原の天然ガス
1911年の新聞記事では、千葉県長生郡茂原地方における天然ガス井の掘削や利用の様子が報じられている。その内容をかいつまんで記すと以下のようになる。
現在、東京から茂原までは特急で52分の距離であるが、当時は汽車で2時間半を要し、天然ガスを除けば唐黍の蔭で蟋蟀が鳴き、鶏が餌を漁っている平凡な田舎に過ぎなかった。天然ガスの試掘作業はいわゆる上総掘の一種と思われ、トタン葺きの小屋の中で二人の男によって行われていた。一人が大きな水車に乗ると、今まで、もう一人が地中へ突き込んでいた長い竹の竿がその水車に巻かれて緩やかに上がってくる。七間ばかりの周囲に九巻きばかり、その先に鉄の機械がついていて、弁を開くと、チュッチュッと泥水を噴くと記されている。これを繰り返して少しづつ掘り進みガス層へ近づいて行くのである。今日から見れば非常にプリミティブな方法であった。
県立農学校の試耕地の傍にある古井戸からは、盛んに紫褐色の水と、こまかな白い泡(天然ガス)が湧いていたと記されているが、水が紫褐色なのはヨウドを含んでいたためであろう。その井戸は記者が訪れる八年前に掘られたものであるが、県有地なので天然ガスが利用されることもなく湧くままに放置されていたらしい。臭いも味も色も無く、その泡に火をつけると非常によく燃えたと云われている。
記者は昌平町の稲荷神社も訪れている。この神社には二つのタンクが据えられていた。朱に塗られたタンクには湧出する天然ガスが溜められ、神前の燈明にもこの天然ガスが使われ、青黄色いガスの光が輝いていた。ここの井戸は1911年の4月5日から掘りはじめられ、96日後の7月10日に初めて噴水し、約373mの深さのガス層に達した。2吋のパイプから1時間に約1万m3噴出するといわれ、250箇所の燈火に使われ、16~30燭光が一番多かったと記されている。
茂原における天然ガスには、二人の恩人がいたと記されている。板川恭太郎氏と千葉弥次馬氏である。板垣氏は1890年に横浜で電燈会社創立の際、その技手であったが、同年7月15日の磐梯山の噴火から暗示を受け、その時以来日本全国の火山を跋渉し、随道工夫、潜水工夫、鉱山工夫になって調べた結果、遂に突然の噴水は必ずしも水圧によるものではなくガスの圧力に原因し、火山の噴水は水蒸気に原因しないことを発見した。地層の深浅、工事の難易はあるにしても地球の至る所に人工の噴火口を開鑿出来ることを悟り、これを多くの学者に提議したが認められなかった。ところが1908年5月になって、同郡鶴枝村の医学士千葉弥次馬氏の知遇を得、翌年5月それまでの観察に教えられた学理を実地に試す機会を得たという。
茂原には丸弁蔵という銭湯があり、天然ガスの井戸を掘って風呂を沸かすのに使用しているということである。
記事によれば、茂原の他に、茨城の平潟町、大津町、磐城の湯本、平、羽後の秋田、相模の小田原等においても掘削が企図され、東京では洲崎の大八幡楼の庭前における掘削が近くガス層に達するとある。天然ガス鉱業組合は、東京を中心として全国に発展することを企図し、当局の許可さえあればすぐにも工事に着手するとかで、東京付近に一大ガス層の存在を確かめたらしいとあり、料金なども人工ガスや電気に比して半分程の廉価を発表したらしく、この事業がうまく行けば人工ガスと電気とは直ちに光を失うかもしれないと記されている。
最後に記者の感想がこう記されている。
「そういう経済上の問題を別としても、天然ガスの掘削という一事が、いかにこの茂原に生気を与えているか、稲の穂や蕎麦の花や甘藷の蔓のみの田園は漸く死滅に近づいて、科学の力を承認した田園がいかに復活するか、その実例をこの茂原にも見ることができた。」
(参考資料 東京ガス がす資料館年報No.3: 原典 読売1911)